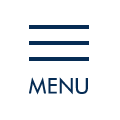スタッフブログ
![]()
台湾出身のスタッフ の記事
-

2025.8.31
日本と台湾の職場文化の違い~台湾から来ました2025!no.4~
こんにちは。台湾からインターンシップで日本に来ました、呉 宜軒(ご ぎけん)です。 新産住拓でのインターンシップもあっという間に1ヶ月が過ぎました。 今回は、私が日本で働く中で気づいた「職場文化の違い」についてお話したいと思います。 台湾出身の私から見ると、日本との違いに驚くことがいくつかありました。今日は、その中でも特に印象的だった4つのポイントをご紹介します! 1.台湾ではスーツを着る人が少ない?! 日本では、街を歩けばスーツ姿のサラリーマンをよく見かけます。私も来日当初、その光景にびっくりしました。 もちろん日本にも服装が自由な会社がありますが、台湾と比べるとスーツを着る割合はかなり高いように思います。 一方、台湾では大手企業であっても、毎日スーツを着る人はそれほど多くありません。カジュアルな服装での出勤が一般的で、仕事でもビジネスカジュアルやカジュアルな恰好でOKな職場が多いです。 「快適で動きやすい」を重視する文化なのかもしれませんね。 2.転職への考え方が違う 日本では、1つの会社に長く勤める方もまだまだ多いようです。もちろん転職経験のある方もいますが、「一生同じ会社で働く」という選択も珍しくありません。 対して台湾では、転職はとても一般的です。給料、職場環境、自分の夢などを考慮してキャリアアップを目指す人が多く、転職はポジティブな選択と捉えられています。 そのため、長く1社で働いている人を見ると「すごいなぁ!」と驚くこともあります。 3.ビジネスの連絡手段も違う? 日本では、LINEは主に友人同士の連絡ツールとされていて、ビジネスの場ではメールが使われることが多いですよね。マナーを大切にする日本らしい文化だと感じています。 一方台湾では、業務連絡にもLINEを使うことがよくあります。返事のスピードや、柔軟なやり取りができる点で便利ですよね。 ただし、日本ではビジネスにおいてはメールなど、フォーマルな手段が好まれるため、場に応じた使い分けが必要だなと感じました。 4.台湾では「挨拶」しない?! 日本の職場では「おはようございます」「お疲れさまです」「お先に失礼します」など、丁寧な挨拶が日常の一部になっていますよね。この文化はとても素敵で、私も今では自然に挨拶が出るようになりました。 でも台湾では、こうした挨拶のやり取りは必須ではありません。出勤しても挨拶を交わさず、そのまま仕事を始めることも普通です。 なので、もし台湾の方と一緒に働く機会があっても、相手が挨拶をしないからといって「無視された」と思わないでくださいね!相手は慣れていないだけかもしれません! 日本と台湾には、似ているようで意外と違う“働き方の文化”があります。 国によって価値観やマナーが異なるのは当たり前なので、「違い」を知って歩み寄ることが、より良い職場づくりにつながると学びました!! これからも、日本の文化を学びながら、自分らしく頑張っていきたいです!皆さまに、展示場やモデルハウスでお会いできるのを楽しみにしています(^^)/▼モデルハウスについてはこちらhttps://sumai.shinsan.com/modelhouse/ ▼イベントについてはこちらhttps://sumai.shinsan.com/event/ 呉 宜軒
詳細を見る -

2025.8.29
日本と台湾のバスに乗る時の違い~台湾から来ました2025!no.3~
こんにちは。台湾からインターンシップに来ました、呉 宜軒(ご ぎけん)です。 今回は、日本と台湾のバスに乗る時の違いについて紹介します! 私が日本に来てびっくりした事の1つだったので、最後まで見ていただければ、うれしいです! ■ICカードの違い 台湾人にとって、日本のICカードといえば「Suica」が代表的です。私も以前は、Suicaは日本全国どこでも使えると思っていました。しかし、実際に日本に来てみると、地域によってはSuicaが使えないこともあると知って驚きました! 台湾にも複数のICカードがありますが、なかでも「ユーユーカード」はとても便利です。ユーユーカードは台湾全土で使え、バスだけでなく、電車やコンビニなどでも利用できます。 また、ユーユーカードにはさまざまなデザインがあり、人気キャラクターとコラボしたものも多くあります。台湾を訪れた際には、ぜひチェックしてみてください♪ ■現金での支払い方法の違い ICカード以外にも、現金での支払いがありますが、実はこの方法も台湾と日本では違います! 日本では、乗車時に整理券を取り、降車時に前方の画面で整理券の番号に対応する運賃を確認し、指定の金額を支払います。 一方、台湾では乗車時に決まった金額を料金箱に入れるだけでOKです。とてもシンプルです! ■台湾では安全意識が低い!? 日本に来て、もう1つ驚いたのは、バスの運転手さんが乗客全員が座るのを待ってから発車することです。 これは台湾では珍しいことです!台湾では、乗客が座る前にすぐ出発してしまうことがよくあります。そのため、すぐに座らないとバスの中で転んでしまうことも…。 台湾でバスに乗る時は、十分注意してくださいね! 8月は、新産住拓の住宅展示場やイベントのお手伝いをすることもあります。見かけた際は、お気軽に声をかけていただけると、うれしいです♪▼モデルハウスについてはこちらhttps://sumai.shinsan.com/modelhouse/▼イベントについてはこちらhttps://sumai.shinsan.com/event/ 呉 宜軒(ご ぎけん)
詳細を見る -

2025.8.26
日本と台湾の飲食店の3つの違い~台湾から来ました2025!no.2~
こんにちは。台湾からインターンシップに来ました、呉 宜軒(ご ぎけん)です。 日本に来て、もう2週間が経ちました。この短い期間でも、台湾と日本との違いにたくさん出会いました。 今回は「台湾と日本の飲食店の違い」について、紹介させていただきます! 【台湾では、水やおしぼりが無い】 皆さんにとって、レストランに行った時にお水とおしぼりを渡されるのは当たり前ではないでしょうか。 実は、台湾ではお水はあっても、おしぼりはほとんど見たことがありません!初めて日本で外食をした時、マスターにおしぼりを渡されて、びっくりしました。 「マスターが情熱的すぎる!おしぼりまでくれた!」と、思ってしまいました。 台湾でおしぼりを渡されると、高級レストランなのかなと思います。 【台湾では、テイクアウトが多い】 日本では、外食をする時、持ち帰りにする人は少ないように感じています。それに対し、台湾では持ち帰りにする人も多いです。 店員さんから「持ち帰りですか?店内でお召し上がりですか?」と聞かれることも少なくありません。 それ以外にも、店内で食べきれなかった料理や飲み物を持ち帰る人も多いです。 しかし、日本では食べきれなかった料理を持ち帰る人は、ほとんどいないと思います。その習慣には、まだ慣れていません! 【「正」の漢字が使われる?】 台湾で食事の注文をしようと思った時、数字の記入方法は普通の数字「1、2、3」と書く以外に、もう1つ方法があります!何でしょう?当ててみてください。 正解は漢字の「正」です! 日本でもこの数え方を使うことがあるそうですが、台湾では主に飲食店で使います。 皆さんも、もし台湾に行くことがあれば、ぜひ使ってみてくださいね! 8月は、住宅展示場やイベントのお手伝いをすることもありますので、見かけた際はお気軽に声をかけていただけると、うれしいです。 ▼モデルハウスについてはこちらhttps://sumai.shinsan.com/modelhouse/ ▼イベントについてはこちらhttps://sumai.shinsan.com/event/
詳細を見る -

2025.8.2
自己紹介「呉 宜軒(ご ぎけん)」~台湾から来ました2025!no.1~
こんにちは、呉宜軒(ご ぎけん)と申します。今年、2ヶ月間の短期インターンシップで新産住拓に参りました。台湾南部の高雄出身で、大学では日本語を専攻しています。 日本に興味を持った理由について高校時代は設計を専攻していましたが、高校3年生になる頃に、だんだん自分には向いていないのではないかと思い始めました。 その時に日本語と出会い、文字の形がかわいいと感じました。また、日本文化にも触れる機会があり、次第に興味を持つようになり、日本が好きになりました! インターンに参加しようと思った理由高校から日本語を勉強し始めて、もう6年になります。しかし、学校以外で日本語に触れる機会が少ないため、会話力や聴解力がなかなか上達しないことに気づきました。 今回のインターンは、日本語能力を伸ばせる良い機会だと考えています。 それに加えて、来学期には4年生となり、もうすぐ社会人として職場に出ることになります。職場やビジネスについても、まだまだ学ばなければならないことが多いと感じています。 趣味について趣味は映画鑑賞です。物語の世界に没入でき、さまざまな人生を体験できるところが、私にとってまるで魔法のような存在です。 現実ではなぜそれが起きたのか分からないことも、映画を観ると一瞬で別の世界に連れて行ってくれるようで、とても面白いと思います♪ 最後に、この2ヶ月間、新産住拓の一員として前向きに頑張ります。 住宅展示場やイベントのお手伝いをすることもありますので、見かけた際はお気軽に声をかけていただけるとうれしいです。どうぞ、よろしくお願いいたします! ▼モデルハウスについてはこちらhttps://sumai.shinsan.com/modelhouse/▼イベントについてはこちらhttps://sumai.shinsan.com/event/
詳細を見る -

2025.2.8
【台湾】「木材生産工場ツアーの感想」~新入社員ユキ no.3~
こんにちは!ユキです。 今回は、「木材生産工場ツアー」の感想をシェアしたいと思います。 去年の10月に入社し、これまで2回のツアーに参加しました。午前中は木材生産を行う「多良木プレカット工場」へ、そして午後には人吉にある「青井阿蘇神社」と「ひみつ基地ミュージアム」に行きました。どれも初めて訪れた場所で、とても楽しかったです!まさに学べる、遊べるツアーだと感じました! 1.自分自身で体験する本社近くの構造館で、住まいの構造や仕様について見学することができますが、実際にプレカット工場に行って体験するのとは全く違うと感じました。工場では、言葉での説明だけでなく、木材に直接触れる機会が多く設けられており、体験コーナーでは、乾燥前と乾燥後の梁の重さ比べをしました。乾燥前の木材は重すぎて、私は全く持ち上げることができませんでした(笑) 2.文化の違い台湾では一戸建てや木造建築はあまりないので、プレカットや木材・乾燥に関する知識を勉強することができました。現地で保管されている大黒柱にはお客様の名前が書かれてあるものもあり、見ているだけで夢を感じました。 いつか!私も新産住拓の家を建てたいです! 3.木の魅力アイデア次第で、様々な活用の仕方や楽しみ方ができると感じました!例えば、カンナくずをアレンジした「ボンボン」!木材の表面をきれいにするためにカンナがけされた薄い削りくずは、多用途で使用することができます。削りたてのカンナくずからは、心地よい木の香りがします。それをアレンジして、丸い形を作ったのがこちらです。 玄関のドアや下駄箱に飾るととても可愛らしいですし、消臭効果もあります。実用的でありながら、美しさも兼ね備えた素敵なアイデアですね!まさに目から鱗が落ちた瞬間でした! 他にも、木材を加工する過程で残った端材は、積み木やコースターとして使用することができます。工場内に設けた休憩&積み木コーナーは、特にお子様に喜んでいただきました。 初めて参加した10月のバスツアーはとても緊張しましたが、しっかり勉強することができました! お住まいづくりを検討されている方で、「もっと新産住拓のことを知りたい方」がいらっしゃれば、絶対に!参加した方がいいと感じました!(^○^)人(^○^) 次回のツアーは、3月・4月・5月に開催します!3月のツアーでは、午後の観光地として「青井阿蘇神社」または「御船町恐竜博物館」のどちらかをお選びいただけます。ご家族やご友人と、ぜひご参加ください!▼イベントの詳細・ご予約はこちらhttps://sumai.shinsan.com/event/details_533.html
詳細を見る -

2025.1.29
【台湾】「春節(旧正月)」~新入社員ユキ no.2~
こんにちは!ユキです。 今回のブログでは、全世界の華人にとって最も大切で伝統的な祝日、「春節(旧正月)」を紹介したいと思います。 年越し準備:街が赤く染まる旧正月の約1ヶ月前から、夜市や大型スーパーはすっかり赤一色になります。赤い飾り物(しゅんれん)や紅包(ほんぱお)が並べられ、町全体が新年の雰囲気に包まれます。 人々は、家に飾るお正月飾りや、年賀用の紅包を購入するために賑やかに買い物をしています。この時期、台湾の街はとても活気に溢れており、旧正月の準備が着々と進んでいきます。 では!早速ですが、我が家の過ごし方をご紹介したいと思います! ■除夕(大晦日):祖先や土地の神様を祀り、囲炉裏を囲んで夜を過ごし、年越しをする除夕の夜は、父方の家族全員が集まり、一緒に「年夜飯(ねんいぇふぁん)」を食べます。年夜飯では、「毎年余裕がある」「豊かである」という意味を持つ魚料理(年年有余)など、縁起の良い料理が並びます。 お互いに「新年快楽(シン・ニエン・クァイ・ラー)」や「恭喜発財(ゴン・シー・ファー・ツァイ)」と言って、良い運を祈ります。さらに、親戚からは「紅包(ほんぱお)」というお年玉が渡され、これは現金が入っており、幸運や健康を願う意味があります。 ■初一(元日):祖母の家で縁起がいい食べ物を食べる元日の朝は、必ず早起きして祖母の家に行きます。そこで、いろいろな縁起のいい食べ物をいただきます。例えば、からし菜(長年菜)は「長寿」、大根餅は「好彩頭(良い運)」、そして豆腐干は「出世」を象徴します。これらの料理を食べながら、新年の始まりを過ごします。 ■初二:母方の実家に帰る初二は「回娘家」と呼ばれる日です。この日は母方の実家に行き、親戚と一緒に食事をします。 ■初三:お寺で健康と平安を祈願する初三には、お寺にお参りに行き、お花見もします。さらに、我が家には灯籠を灯す習慣があります。これは新しい年の始まりに、神様に祈りを捧げて、家族の健康や安全、幸運や繁栄を願う儀式です。 ■初四と初五:家族との豪華な宴会 - 「バンゾウ」文化初四と初五は、年に1度、親戚が集まって豪華な食事を囲む大切な日です。 特に注目すべきは、「バンゾウ」という台湾の伝統的な宴会スタイルです。道端や広場にテントを設置し、1つ1つの丸いテーブル(円満)を並べて大皿に盛られた料理を皆で一緒に食べます。 台湾で定番のカボチャの種とビスタチオのおつまみも、宴会の最初にテーブルにおいています。さまざまな豪華な食事の中で特に人気なのが「佛跳壁」です。この高級料理は、エビのヒゲ、ホタテ貝などの珍しい食材を使い、長時間煮込んで作るスープです。濃厚で豊かな味わいが特徴です。 また、旧暦1月5日は「財神(ざいしん)」がやってくる日とされており、花火や爆竹を打ち上げて財神を迎えます。 初五(休み明け)は、通常の生活に戻り始めます。これは新年の仕事始めを意味し、順調な1年を祈るために、神様にお参りする習慣もあります。 以上が、我が家の過ごし方です。 私のブログを通して、皆さんにもっと台湾のことを知っていただければうれしいです!♪これからも、たくさんの台湾文化を紹介したいと思っています!台湾に関連する話題は、ほかのブログでもご紹介しています。ぜひご覧ください! ▼台湾についてhttps://sumai.shinsan.com/blog/?tag=16
詳細を見る -

2025.1.25
【台湾】自己紹介!~新入社員ユキ no.1~
こんにちは!ユキです。昨年、新入社員として新産住拓に入社しました! 台湾・台北出身の都会育ちです。大学時代には東京に留学した経験もありますが、人が少ない田舎が好きです。 なぜ「ユキ」と名乗るのかとよく聞かれるのですが、幼稚園の頃に先生から名付けていただいた英語の名前です。 初めてのブログとなる今回は、私の自己紹介をします! ■日本に興味を持つ理由小学生から、週末は必ず姉と一緒に日本の最新のアニメを見ていました。そのため、日本語を学ばなくても、自然と日本語を話すことができるようになりました。姉とはよく、両親の前で日本語で秘密の話をしています!笑日本のアニメ、ドラマ、歌などの文化はいつも私の心に響き、どんな挑戦にも立ち向かう勇気を与えてくれます。 ■新産住拓に入ったきっかけ最初はホームページで見て会社について知りました。「熊本の木の暮らし」の雰囲気と「お客様のために最良の住まいを探求し続ける」という理念がとても好きで、「絶対、内定もらいたい!」と思い、応募しました。建築の知識はゼロで入社しましたので、休日を利用して勉強に励んでいます! ■趣味・旅行日本が大好きで大好きでしょうがないので、29の都道府県に旅行したことがあります。その中でも、特に好きなのは岐阜県と北海道です!長野県の上高地も「神降地」とも言われるように、綺麗で印象深かったです。 ・カラオケ日本のカラオケは安いので、よく一人で行きます!日本の歌は何でも聞いていますが、特に好きな歌手はAdo、ヨルシカです。上手ではないですが、いつも感情を込めて熱唱しています♪ 新産住拓では、最初で唯一の台湾出身社員として、プロの通訳になりたいです。プロになるにはまだまだですが、経験を積んで全力で進んでいきます!!!台湾のお客様の視点から住まいづくりを考えて、幸せになっていただくことを目指しています!! これから、モデルハウスやイベントでお会いすることがあるかもしれません。もし台湾に興味がある方がいらっしゃれば、ぜひ、私とお話ししましょう!▼新産住拓のモデルハウスについてはこちらhttps://sumai.shinsan.com/modelhouse/ 今後のブログもチェックしていただけたらうれしいです。宜しくお願いいたします!
詳細を見る -

2024.9.21
2ヶ月のインターンシップを振り返って~台湾から来ました! no.11~
こんにちは。台湾からインターンシップに来ています、朱です。 2ヶ月のインターンシップがもうすぐ終わりを迎えようとしています。最初は「2ヶ月って長いなぁ」と思っていましたが、気がついたら、あっという間に過ぎてしまいました。今回のインターンシップを通じて、私は多くの貴重な学びと成長の機会を得ることができました。 まず、初めて日本の企業で働くことで、日本の働き方やビジネス文化について深く理解することができました。日本の企業文化は、計画と徹底した準備を重視しており、各プロジェクトの進め方において非常に参考になりました。 特に、様々なミーティングに参加することで、日本のビジネスシーンにおいて情報共有や意見交換が非常に重要であり、全員がより良い結果を目指している姿勢を強く感じました。また、会議でのディスカッションの進め方や、意見が異なる場合の対応方法など、今後のキャリアに役立つスキルを学ぶことができました。 業務においては、特に現場見学や地鎮祭に参加することで、日本の建築業界における現場の雰囲気や作業の進め方、そして日本の伝統文化を実際に体感することができました。現場で働く大工さんたちの姿を目の当たりにし、その専門知識や技術力に深い感銘を受けました。特に地鎮祭では、日本の古くからの伝統を尊重し、現在も大切にしている文化を体験することで、日本と台湾の文化の違いを改めて実感しました。このような日本独自の文化や伝統に触れることは、私にとって非常に特別な経験となりました。 また、他の業務を通じて新しいスキルを習得する機会も多くありました。翻訳の仕事では、単なる言葉の変換だけでなく、相手の意図を正確に伝えるための表現の選択や、文脈に合わせたニュアンスの調整が必要であることを学び、非常にチャレンジングな仕事だと感じました。同時に、言語の壁を越えてコミュニケーションを図る難しさと、それを乗り越えたときの達成感を強く感じました。 そして、チラシやPOPの作成では、視覚を通じて情報を伝える手段の重要性を学びました。画像1つ1つに込められた意味や、お客様にどのように伝えるかが求められました。その結果、効果的なコミュニケーションの手段としての視覚の力を実感しました。 今回のインターンシップを通じて得た多くの知識やスキルに加え、日本の社会や文化に対する理解も深まりました。特に、日本のビジネスシーンで重要視されるチームワークやコミュニケーションのあり方、計画性と準備の徹底など、これまでの自分の考え方に新たな視点を加えることができました。また、日本と台湾の文化の違いを体感することで、異文化理解の大切さを改めて実感しました。 今回のインターンシップで学んだことや感じたことは、今後の私のキャリアにおいて大きな財産となるでしょう。この経験を活かし、今後も自己成長を続けるとともに、異なる文化や価値観を尊重しながら、国際的な視野を持ち、自分でも誇りに思える仕事をしていきたいと思います。 これまで、ブログを読んでいただいた皆様、ありがとうございました! 私たちのブログが、少しでも台湾について知ったり、興味を持ったりするきっかけになっていればとてもうれしいです。▼これまでのブログはこちらからhttps://sumai.shinsan.com/blog/?tag=15 私たちも好きになった「新産住拓の木の家」。まだご覧になったことのない方は、ぜひ一度モデルハウスに足を運んでみてください(^^)▼モデルハウスについてはこちらからhttps://sumai.shinsan.com/modelhouse/
詳細を見る -

2024.9.20
台湾の暮らし「昼寝文化」~台湾から来ました! no.10~
こんにちは、歩です。 突然ですが、皆さんは「昼寝」をしますか?台湾では昼寝の習慣があるので、私が7月に新産住拓に来てまず驚いたのは、お昼休みに誰も昼寝をしていなかったことでした。気になって調べてみたら、そもそも日本には昼寝をする習慣がないことがわかりました。 今日は台湾の「昼寝」について簡単にご紹介します。 ■幼稚園から続く昼寝習慣台湾の学校では、幼稚園から大学生まで、昼寝が日常の一部となっています。昼食後に約40分の昼寝タイムが設けられており、学生たちは机に突っ伏して休憩をとります。マットレスを敷いて布団をかけるような贅沢な昼寝ではなく、あくまで簡単な休憩スタイルです。 昼寝は強制参加で、眠くなくても机に突っ伏していなければなりません。昼寝タイム中には風紀委員や先生が廊下をパトロールし、目を閉じていない生徒を注意します。 注意されたクラスは減点され、減点が少ないクラスが全校朝礼で先生に褒められ、皆に拍手されます。さらに、“いい子のプレート”を校長先生からもらい、廊下に掲げられます。学生たちは少し恥ずかしがりますが、先生にとっては非常に誇らしいことです。 私のように元気な子はどうしても眠れず、先生に叱られたり罰を受けたりしていました。当時の私にとって、昼寝タイムは辛い時間でした。 ■職場での昼寝こうした教育背景から、社会人になっても昼寝習慣を持ち続ける人が多いです。台湾の有名な水餃子屋さん「ディンタイフォン(鼎泰豐)」では、社員が昼食後に短時間休むための休憩スペースや昼寝室を提供しています。私の父も学生時代のように、20分の昼食後に40分の昼寝をします。父は短い昼寝が疲労感を減らすと言って、机で使える昼寝用まくらも購入しました。 ■なぜ昼寝が大事?研究によると、短時間の睡眠はその後の仕事の効率をアップさせるという結果が出ています。いつか日本でも昼寝の習慣が広がるといいですね。 以上で、今回のブログを終わります。 最後に、イベントの紹介です。7月に私たちも参加したバスツアーイベントが、秋にも開催されます!新産住拓の木材のこだわりを肌で感じることのできるイベントです。午後は2コースから選べる観光も楽しめます。9月開催分の募集は終わってしまったのですが、10月・11月も開催予定です(^^) バスツアーに参加してみての感想を、以前のブログで書きました。よろしければ、こちらもご覧ください。▼ブログはこちらからhttps://sumai.shinsan.com/blog/details_778.html
詳細を見る