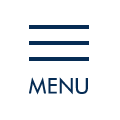スタッフブログ
![]()
- これで解決!お住まいづくりの“ハテナ” vol.13「2019年問題は大丈夫?これからの太陽光発電!前編」
こんにちは!
熊日RKK住宅展の井上です。
“ハテナ”シリーズ、第13弾をお届けします!
今回のテーマは『太陽光発電』です。
最近、また太陽光発電が話題となっていますので、前編・後編の2部構成でお届けいたします!
皆様、唐突ですが、「2019年問題」という言葉を耳にされたことはございますでしょうか?
2019年問題とは、簡単に言うと、
太陽光発電で余った電力(余剰電力)の買い取りが終了してしまうという問題です。
ここだけ読むと
「これから太陽光を搭載しようと思っていたのに」
という方は不安になられたことだと思います。
でも、ご安心ください!
太陽光発電の買取期間は搭載容量によって決められています。
家庭用の太陽光発電(10kw未満)の買取期間は10年間となっており、
買い取りが2009年にスタートしてから10年後にあたる今年、
10年間売電してきた方の買い取りが終わるため、
11年目以降はどうなるのかが問題視され、
2019年問題といわれるようになりました。
(※詳しくは経済産業省資源エネルギー庁のHPをご参照ください)
ではここで、太陽光発電の買取制度について、今一度見ていきましょう。
そもそも、固定買取制度とは何でしょう?
これは太陽光だけでなく、風力発電や水力発電など
再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。
(経済産業省資源エネルギー庁HPより引用)
そして先述した通り、太陽光の買取期間は搭載容量によって定められています。

上図をご覧の通り、買取期間は10kw未満が10年間、10kw以上が20年間となっております。
また、今年度の売電価格は10kw未満が26円、10kw以上が14円+税となっております。
(※九州電力圏内は出力制御機器設置義務があります。)
一時期は住宅でも10kw以上の大容量の太陽光を搭載して売電収入を得ることのできる住宅が人気になりました。
しかし、2014年のいわゆる九電ショック以降、売電収入を得るという考え方から、
自家消費分で家庭の電気代を賄うという考え方に切り替わってきました。
それに追い風になるように、
2015年のパリ協定や近年のSDGsなど気候変動に対する世界的な取り組み、
そして、以前の私のブログでも紹介しましたZEHやLCCM住宅の普及により太陽光発電も比例して増えてきました。
むしろ、現在の新築住宅では太陽光を搭載している住宅が標準的となってきました。
これからご検討されるお住まいは本当にZEHですか?
これからは太陽光発電が搭載されている住宅が一般的となってきますので、ぜひご参考ください!
次回は後編再エネ賦課金って何?をお届けいたします!
新産住拓のZEHはこちら
~熊本の住まいは熊本の木で~
熊日RKK住宅展 井上大樹